2019年に公開された映画『キングダム』。原作は累計1億部を超える人気漫画だが、今回はあくまで原作未読の視点から、映画だけを観た人間として語らせてもらう。
結論から言おう。
これは、金をかけた学芸会である。
基本情報
タイトル:キングダム
公開日:2019年4月19日
上映時間:134分
ジャンル:歴史アクション/時代劇
製作国:日本
監督:佐藤信介
脚本:黒岩勉、佐藤信介、原泰久(原作者)
原作:原泰久『キングダム』(集英社「週刊ヤングジャンプ」連載)
音楽:やまだ豊
主題歌:ONE OK ROCK「Wasted Nights」
配給:東宝/ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント
興行収入:約57億円
受賞歴:第43回日本アカデミー賞 優秀アクション監督賞、話題賞など
あらすじ
舞台は中国・春秋戦国時代末期、戦乱の世。
戦災孤児の少年「信」と「漂」は、日々剣術を鍛えながら“天下の大将軍になる”という夢を抱いていた。ある日、漂が王宮に召し上げられ、2人は別々の道を歩むことに。
しかし、王宮では政権を狙う王弟・成蟜(せいきょう)によるクーデターが勃発。命を落とした漂は、信に地図を託して息絶える。信は地図の示す場所で、漂と瓜二つの少年・嬴政と出会う。実は彼こそが、秦国の若き王だった──。
天下の命運を賭けた、王と少年の“運命の共闘”が、ここから始まる。
一言で言うと「痛い」。いや、観てて恥ずかしくなるレベル。

物語の舞台は紀元前245年、中国の春秋戦国時代。孤児の少年・信(しん)が天下の大将軍を目指し、乱世を駆け抜ける王道の英雄譚だが、演出のすべてが浮いている。
セリフ回しがとにかく不自然でアニメ的なのは仕方がないのは理解しているつもりだが、やっぱり「寒い」空気が漂う。
これは永遠の課題だが、漫画のキャラをそのまま実写に持ち込むと、ギャップと違和感しか残らない。かと言って原作から変えると原作と違う!とかぬかすファンがいるから漫画からの実写化は映画製作人たちにとってはかなり厄介なジャンルである。
セット感丸出し。
衣装、小道具、ロケーション。どれをとってもいま撮りました感が抜けない。
たとえば戦闘シーン。カメラはやたらとブレてるが、アクションの凄みは伝わらない。むしろ「マトリックス」の劣化コピーのようなワイヤーアクションが虚しく回転するだけ。
衣装も新品同様で、戦い抜いてきた者たちの生活感がゼロ。
彼らの眉毛も整いすぎていて、もはや紀元前ではなく渋谷の美容室帰りの若者にしか見えない。
過剰な演技。動物園か?
役者たちは皆、叫ぶ。怒鳴る。吠える。ギャーギャーと五月蝿いだけで、感情が乗っていない。動物園の檻を開け放ったようなカオス。
主演の山﨑賢人には申し訳ないが、観ていて顔が赤くなるほどの演技だった。演技というよりはやってます感。それを受けて周囲の俳優たちもどんどん舞台芝居じみていく。
キャスティングの美男美女主義

ここで指摘したいのが、日本映画界に蔓延する「イケメン・美女しか出さない」病だ。
確かに見栄えはいいが、それが紀元前のリアルさをすべて台無しにしている。
肌が綺麗、メイクもバッチリ、骨格も令和。何もかもが今どきで、タイムスリップしているのはこちら側だ。
なぜこれが大ヒットしたのか?
興行収入57億円を超え、続編も作られるほどの成功を収めた本作。だがその裏には、「原作ファンによる集団動員」と「邦画離れを食い止めたい業界の推し」の存在があるだろう。
本来、映画というものは原作を知らない人でも楽しめる普遍的な表現であるべきだ。
だが『キングダム』は、あまりに原作依存で、外部の視点を無視した内輪ノリの映画になってしまっている。
日本映画が乗り越えるべき壁
この作品が見せたのは、「実写化の難しさ」だけではない。演技、演出、セット、脚本、すべてに対しての覚悟のなさが透けて見えた。
美しく、カッコよく、無難に。そんなものを積み上げたところで、心は揺さぶれない。
映画というのは、もっと泥臭く、もっと本気でぶつかるべきだ。
結論:これは“映画”ではなく“コンテンツ”
『キングダム』は映画ではない。映画風パッケージのメディア商品である。
だが、これを良いと思う人が多いなら、それはそれでいいのかもしれない。
ただし、これが「日本映画の代表」と言われたら──
俺は全力で否定する。
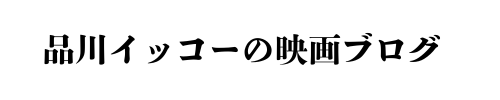



コメント