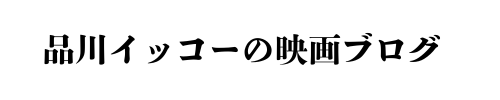2022年にアメリカで公開され、2023年には日本でも話題を呼んだ映画『ザ・ホエール(The Whale)』。
主演はかつて『ハムナプトラ』シリーズで人気を博したブレンダン・フレイザー。
彼の圧巻の演技により、第95回アカデミー賞で主演男優賞を受賞し、まさに“奇跡のカムバック”として大きな注目を集めました。
この記事では、映画『ザ・ホエール』のあらすじや見どころ、評価、ブレンダン・フレイザー復活の背景について深掘りしつつ、なぜこの作品が世界中の映画ファンの心を動かしたのかを解説します。
基本情報
作品名:『The Whale(ザ・ホエール)』
公開年:2022年(日本公開は2023年4月7日) 監督:ダーレン・アロノフスキー(『ブラック・スワン』『レスラー』など)
脚本:サミュエル・D・ハンター(自身の舞台劇『The Whale』が原作)
ジャンル:ヒューマンドラマ
上映時間:117分
製作国:アメリカ 配給(日本):キノフィルムズ
主演:ブレンダン・フレイザー(チャーリー役)
制作会社:A24
主な受賞歴: 第95回アカデミー賞 主演男優賞(ブレンダン・フレイザー)
同 助演女優賞ノミネート(ホン・チャウ)
同 メイク・ヘアスタイリング賞 受賞
あらすじ
舞台はアイダホ州のアパート。
チャーリーという体重約270kgの男性が、ほとんど外出せず、オンライン授業の講師をしながら孤独に暮らしている。過食症に苦しみ、死期が近いことを悟った彼は、疎遠になっていた17歳の娘エリーと再び心を通わせようとする。
ブレンダン・フレイザーの復活劇が泣ける

しかし驚いた。かつて「ハムナプトラ」で一世を風靡した俳優ブレンダン・フレイザー。
彼はハリウッドの大物にセクハラされたことがきっかけで鬱状態に陥り、45キロも激増。
「あの人はいま?」状態となり、舞台からすっかり消えてしまった悲しい俳優の1人である。
その相手とは、ゴールデン・グローブ賞などで知られるハリウッド外国人映画記者協会の当時の会長だったフィリップ・バーク。
そんな彼がカムバックということでこの映像を見た。
「太った」という話は聞いたことがあるが、まさかここまではとは…
と思ったら特殊メイクかよ!
二足歩行でまともに歩くこともできない272キロの巨体の男チャーリーを演じてます。
うわー、なんか90年代〜2000年代の映画を観まくってたものとしてはすごく感慨深い。確実に人は歳をとるし、当然自分も老けてる。
なんとこのメイクにかかった時間は4時間超で、撮影期間はおよそ40日間に及んだそう。役者もスタッフも大変だなぁ。
イケメンなので太ってもどこかチャーミングではあります。
なぜ『ザ・ホエール』は暗く、映像比率が3:4なのか?
映画は基本的に部屋の中。そしてとにかく部屋が暗い。なんで?
多くの視聴者が疑問に思うのが、
「なぜこの映画はこんなに映像が暗いのか?」
「なぜ3:4という珍しい画面比率なのか?」
という点です。
これは、監督ダーレン・アロノフスキーの演出意図によるもの。
チャーリーの「閉塞感」「孤独」「身体的な不自由さ」を、映像で視覚的に伝えるために、あえて窮屈で暗い構図を選んでいる。
常に狭く、息苦しい画面は、チャーリーの人生そのものを象徴しているわけだ。
えー、観るだけでストレス…
『ザ・ホエール』の評価|なぜ賛否が分かれるのか?
本作の評価は高く、アカデミー賞受賞やA24作品としての品格もありつつ、一方で「退屈だった」「映像が暗すぎる」「エリーの態度が不愉快」といった声も一定数あります。
僕もその意見に同意。
完全に今までの作品に比べてもテンポが悪い。
今時の人間アピールしたくはないが、基本的にワンシチュエーションていくらなんでも展開がなさすぎるのだ。
静かに淡々と進む物語にカタルシスを求めると、物足りなく感じるかもしれない。
しかし、それこそが本作の魅力。リアルな「人間の再生」を描いているからこそ、万人受けはしない。
タイトル『ザ・ホエール』の意味とは?
「鯨=チャーリーの体型を揶揄しているのでは?」と思うかもしれないが、実はこのタイトルにはもっと深い意味がある。
チャーリーは、授業で「白鯨」のレポートを読むよう学生に課している。
そして映画の最後、娘エリーが朗読するその文章に、チャーリーが唯一救われる瞬間が訪れる。
鯨は象徴であり、彼自身であり、娘との和解の象徴でもあるのだ。
まとめ
『ザ・ホエール』は決してエンタメ作品ではないが、人生で誰もが抱える「後悔」「孤独」「許し」を真正面から描いた、静かで深い映画だ。
ブレンダン・フレイザーの名演技が心に残るのは間違いない。
90年代の彼を知っている人には、なおさら感慨深いはず。
評価が分かれる作品だからこそ、自分自身の目で確かめてほしい一作だ。
僕はもう見たくない否のタイプだけど。